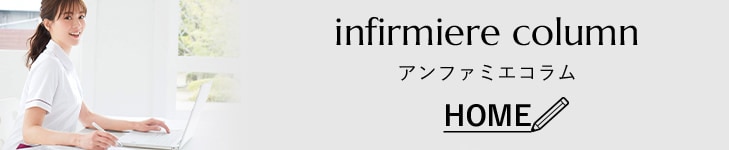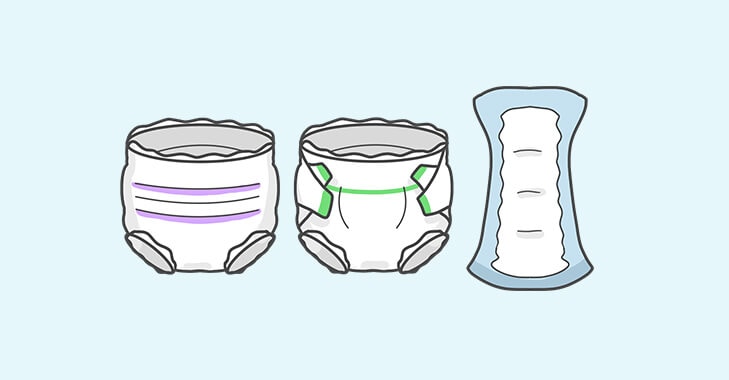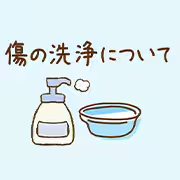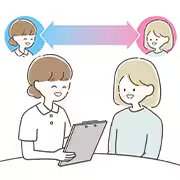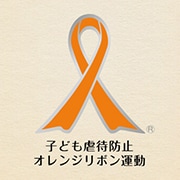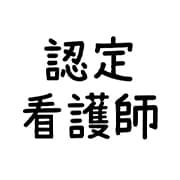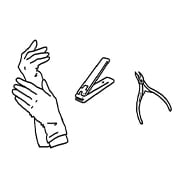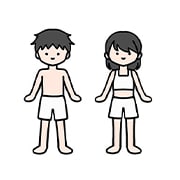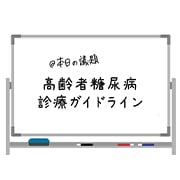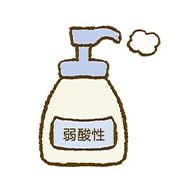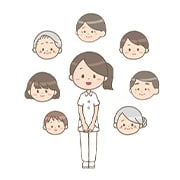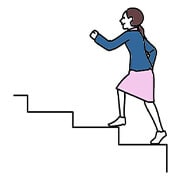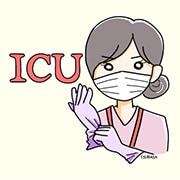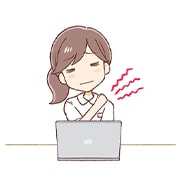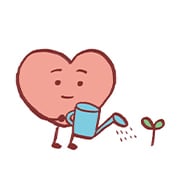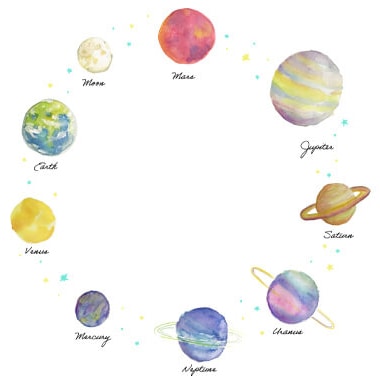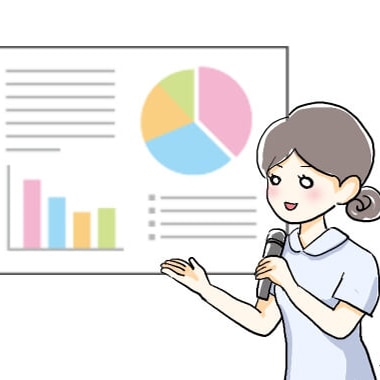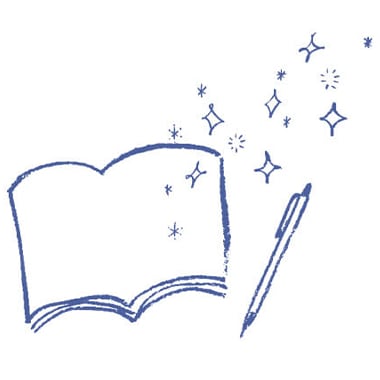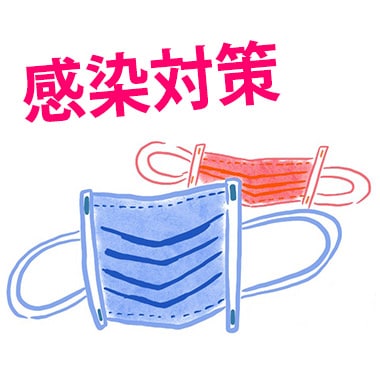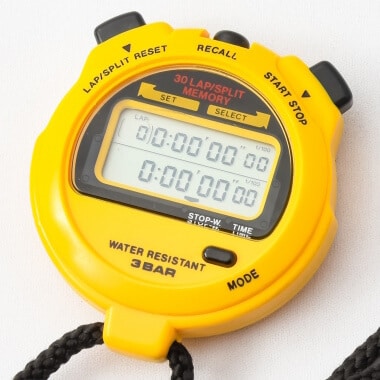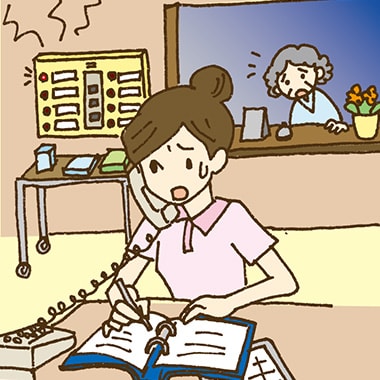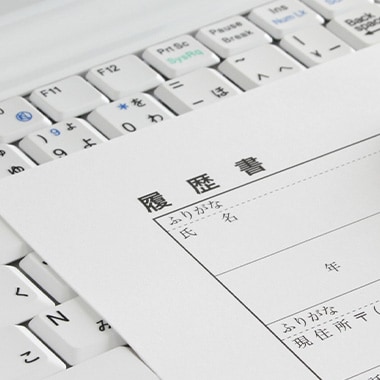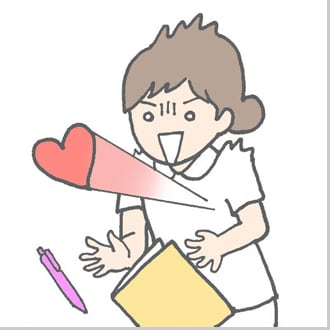そもそも病児保育とは
病児保育とは、病気の子どもを一時的に預かって保育や看護を行うものです。保護者の就労などで、病中・病後の子どもを自宅で看ることが難しい場合に利用が可能です。
病児保育には、医療機関や保育所の専用スペースを利用する「病児対応型」「病後児対応型」「体調不良児対応型」と、看護師などが自宅へ訪問する「非施設型」(訪問型)があります。
病児対応型
病気の回復期に至っておらず、集団生活が難しい児童を一時的に預かるもの。実施場所の多くは、病院や診療所となる。
病後児対応型
病気の回復期にあるものの、集団生活は難しい児童を一時的に預かるもの。主に保育所を実施場所としている。
体調不良型
保育施設での保育中に体調不良となった児童を、保護者が迎えに来るまでの間、医務室などで一時的に預かるもの。
私は第一子が1歳4ヶ月、第二子が7ヶ月のときに仕事復帰しました。子どもが0~3歳頃までは体調を崩すことが多く、診療所に併設する病児対応型には何度もお世話になりました。
病児保育を利用するメリット
病児保育を初めて利用したときは、病気の子どもを預けて仕事へ行くことに罪悪感を抱きました。しかし、実際に利用してみると、以下のようなメリットを感じたのです。
看護師がいるため安心して預けられる
病児保育には、人員配置や医療機関との連携体制などに関して、さまざまな規定が設けられています。病児対応型であれば、原則として利用児童おおむね10名につき、1名以上の看護師を配置しなければなりません。
私が利用していた病児保育には1~2名の看護師が常駐していたため、発熱や咳などの症状がある子どもを安心して預けることができました。
個々の体調に応じて柔軟に対応してくれる
同じ発熱している子どもでも、横になって眠りたい子がいれば、おもちゃで遊んで過ごしたい子もいます。病児保育では、医師の診察結果や子どもの体調などをふまえて、個々の状況に合わせた過ごし方ができるよう配慮してくれます。
自治体の補助があれば低価格で利用できる
私が住んでいた自治体には、病児保育の利用料が補助される制度がありました。料金の高さを理由に、病児保育の利用を躊躇することがなかったのはありがたかったです。
夫婦間のもめ事が減る
子どもが頻繁に体調を崩すと、看病だけで有給を消化してしまうことがあります。
わが家は両実家が遠方で頼れる人がいなかったため、夫婦のどちらが休みを取るかでもめることがありました。「夫婦がどちらも休めないときは病児保育に頼る」と決めてからは、夫婦間のバトルが激減しました。

病児保育を利用するデメリット
一方で、病児保育を利用することには、いくつかのデメリットがあります。
受け入れ定員が少なく予約が取りにくい
私が利用していた病児保育は、1日の受け入れ定員が10名でした。近隣で病児保育を実施している施設は少なかったため、予約が取れず利用できない場合もありました。

保育園よりも送迎に時間がかかる
病児保育を利用する際、事前にかかりつけ医を受診する必要があります。利用時間が保育園より短かったこともあり、職場に事情を話して始業時間を遅らせたり、早めに退勤させてもらったりする必要がありました。
持参する荷物が多く準備に時間がかかる
私が利用していた病児保育では、着替えやおむつ、布団などのほかに、昼食やおやつも持参する必要がありました。朝の準備にはいつも以上に時間がかかるため、病児保育で必要になる荷物をリスト化しておき、すぐに荷造りできるようにしていました。
まとめ
病気の子どもを預けられる病児保育は、子育て中の看護師が知っておきたい社会資源の一つです。子どもたちが大きくなるにつれて利用頻度は減りましたが「いざというときは病児保育に頼れる」という安心感が私の心の支えになっていました。
出産後の働き方に不安を感じたら、家族や保育園以外に頼れる場所を見つけておくことで、仕事と育児を両立している自分がイメージしやすくなるかもしれません。
ライタープロフィール
【よしわら かおり】ナースLab認定ライター
仕事と家庭の両立に悩み続け、ライフスタイルの変化にあわせて4度の転職を経験。「ナースでも在宅で働きたい」という思いから、現在はライターや産業保健師として活動中。プライベートでは2児の母。
ポートフォリオ:https://note.com/kaorin09/
ナースLabホームページ