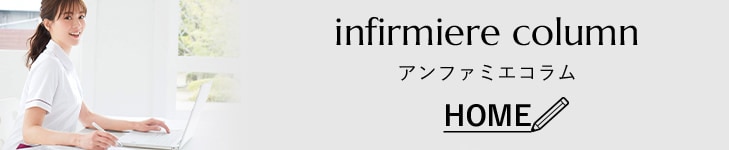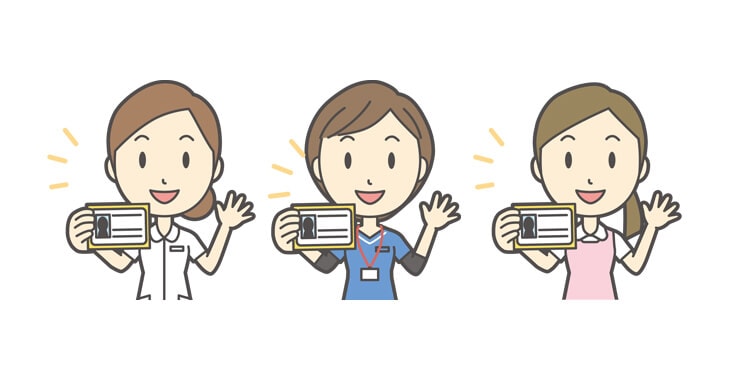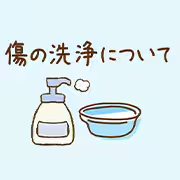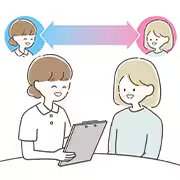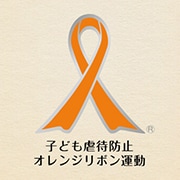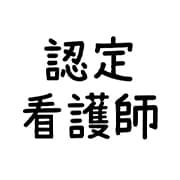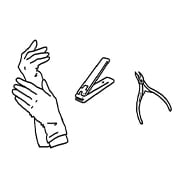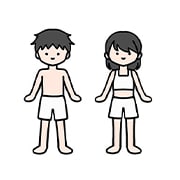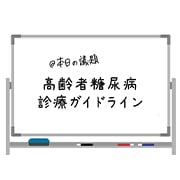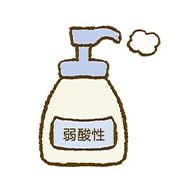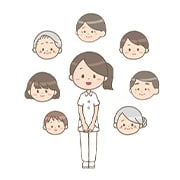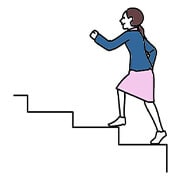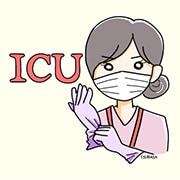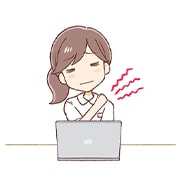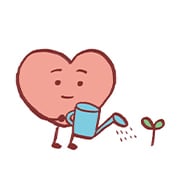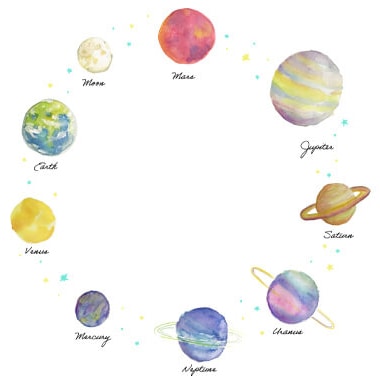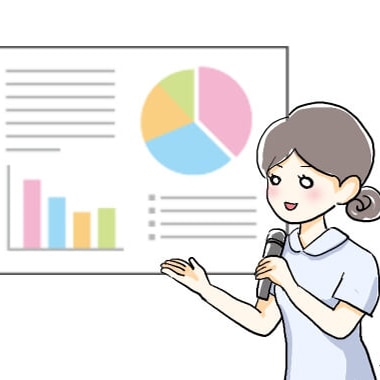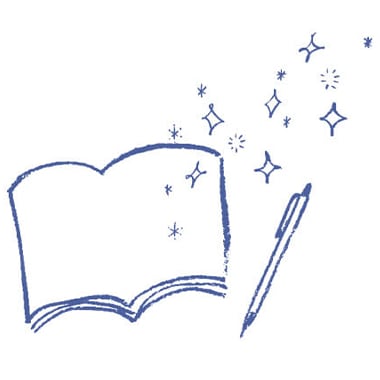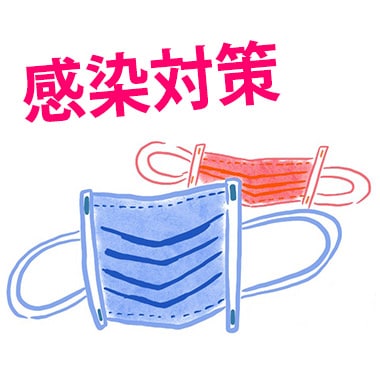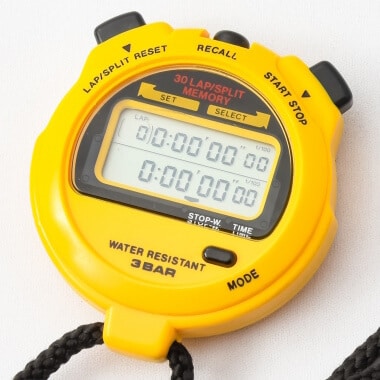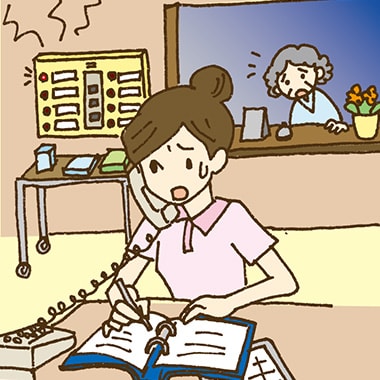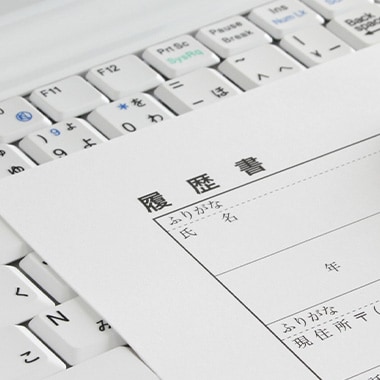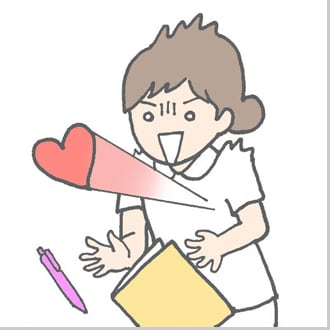1.褥瘡裁判で負ける理由は明確
褥瘡裁判は、褥瘡の悪化で死亡したと訴えられるケースが多く、医療者側が適切な予防ケアや治療を行なっていたか否かが争点です。
過去の褥瘡裁判を紐解いてみると、2つの共通点がありました。
① 褥瘡の発生や悪化を予測できていたか?(注意義務)
② 予防のための対策を実施していたか?(安全配慮義務)
これらを行わなかった、もしくは実施を証明できない場合、行うべき義務を怠った(=債務不履行)と判断されます。
過去の裁判では、病院側が人員不足のため体位変換を2時間ではなく3時間ごとと決め、その実施も証明できず敗訴となった例がありました。2)
褥瘡のリスクよりも、人員不足が理由で体位変換を3時間毎と決めていた点が注意義務違反、実施記録が不十分だった点が安全配慮義務違反に当たります。
ちなみに最新の褥瘡予防・管理ガイドライン第5版では「体圧分散マットレスを使用したうえでの4時間をこえない体位変換間隔を提案する。2B」3)とあります。体位変換間隔は、2時間にこだわるよりも褥瘡のリスクに合わせて決めるべきです。
話を戻します。
もし、褥瘡の悪化を早々に予測できていたら?
関わった医療者の予防意識が変わっていたのではないでしょうか。
患者家族に悪化予測やその後の経過を説明していたかも知れません。
褥瘡裁判も防げたのでは?と想像します。
では、褥瘡の悪化はどのように予測すればよいのでしょうか?
2.勝負は褥瘡の急性期
褥瘡の悪化予測は、全身と褥瘡局所の2つの視点でアセスメントします。
全身のアセスメントは、体位変換能力や栄養状態などを評価する、お馴染みの褥瘡リスクアセスメントです。ブレーデンスケールや厚生労働省の褥瘡危険因子評価、OHスケールなどが一般的です。これらは、入院時以外にも全身状態が変化した際に評価することで、褥瘡の悪化予測ができます。
褥瘡局所のアセスメントは、悪化予測が難しい急性期に絞って述べていきます。
発生後3週間は、日毎に褥瘡の表情が変化する時期です。たとえば、仙骨部に発生した発赤が赤紫色や暗紫色へ変化したと思ったら、黄色や黒色の壊死組織に穴が空いてポケットに至る褥瘡。このような褥瘡は、DTI(深部損傷褥瘡)といわれ「表皮剥離のない褥瘡(stageⅠ)のうち,皮下組織より深部の組織の損傷が疑われる所見がある褥瘡をいう。」4)と定義されています。
褥瘡は、皮膚表面から皮下に深掘っていくものと、皮下組織や筋肉組織が先にダメージを受け表面化するものがあります。DTIは、後者の経路を辿るため、深い褥瘡になることが早い段階で予測できるのです。
さらにこの時期は、全身状態や栄養摂取量の低下など、褥瘡の悪化要因も同時発生しています。
したがって、看護師が毎日観察して体位変換しても「入院して褥瘡ができた」、「適切なケアをしてもらえなかった」と見えてしまいます。
一方、発赤が数日後に消失し、治癒する褥瘡もあります。
確かなことは、褥瘡の発赤は経過を追わないと変化をつかめないことです。判断がつく頃には、すでに悪化した深い褥瘡になっていることがあります。
私たち医療者ができることは、褥瘡リスクアセスメントで全身を評価し、褥瘡の発見時にDTIの有無を確認し、適宜本人と家族に状況説明する。この3点に尽きます。
3.褥瘡発見時にDTIを疑う
2020年に改訂された褥瘡状態評価スケールDESIGN -R2020では、「DTI疑い」の項目が新設されました。判断方法に関する注釈には、視診、触診 補助データ(発生経緯、血液検査、画像診断等)とあります。5)視診や触診は、褥瘡治療に関するプロフェッショナルな経験値が必須です。CTやサーモグラフィー、エコーなどの画像診断は、客観的かつ明確な判断方法です。その中で、タイムリーかつ経時変化を追いやすいエコーは、看護師も実施できるのでお勧めです。
エコーを活用すれば、褥瘡の悪化予測が可能です。さらに褥瘡の写真とDTIのエコー画像を患者家族と共有すれば、現状と悪化予測の説明に対し理解を得やすいのではないでしょうか。
まとめ
褥瘡裁判で争点となるのは、褥瘡発生や悪化予測に関する注意義務と適切な体位変換や処置などの実施に関する安全配慮義務です。それらを証明するための看護記録は必須です。
今回は、悪化予測が難しい急性期褥瘡のDTIに注目して述べてきました。もちろん、慢性期の褥瘡の悪化やポケットの拡大方向もエコーで予測できます。詳しくは触れませんでしたが、褥瘡エコーは、悪化予測の強い味方です。
以上を踏まえて、怖~い褥瘡裁判に巻き込まれないよう褥瘡対策していきましょう。
引用・参考文献
1) 裁判所HP:地裁民事第一審通常訴訟事件・医事関係訴訟事件の認容率(最終閲覧日 2022年8月16日)
2) メディカルオンライン医療裁判研究会 :褥瘡予防・管理に関する法的責任(最終閲覧日 2022年8月21日)
3) 日本褥瘡学会:褥瘡予防・管理ガイドライン 第5版 2022年 P17
4) 日本褥瘡学会用語集:(最終閲覧日 2022年7月24日)
5) 一般社団法人日本褥瘡学会:褥瘡状態評価スケール 改定DESIGN-R2020 コンセンサスドキュメント 照林社 2020年 P5
ライタープロフィール
【浦田克美】
東葛クリニック病院主任。皮膚・排泄ケア認定看護師、特定看護師(創傷管理分野)、おむつフィッターの資格を取得。看護師経験25年。
褥瘡ケアと仲間作りを目的に毎月YouTube LIVEで情報発信中。
松戸褥瘡ケアフォーラム公式LINE
→https://lin.ee/h8TWpdD