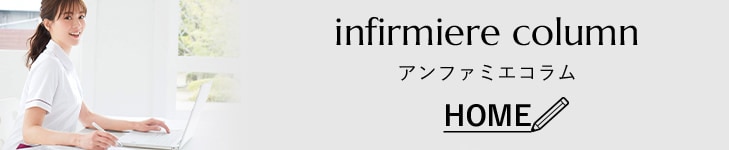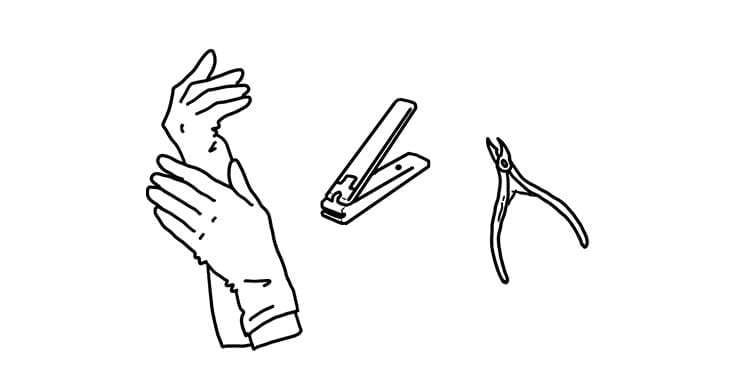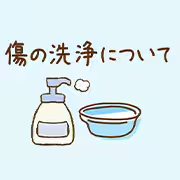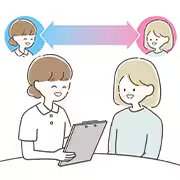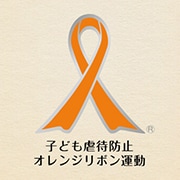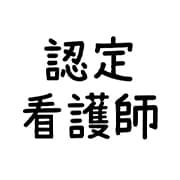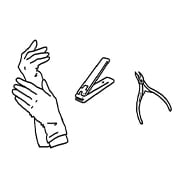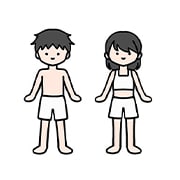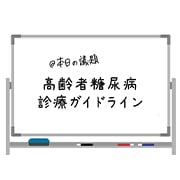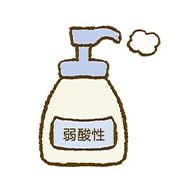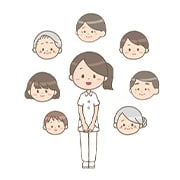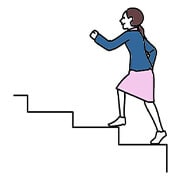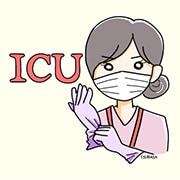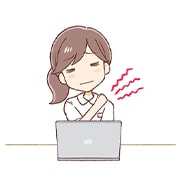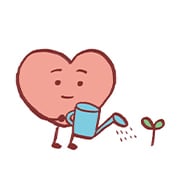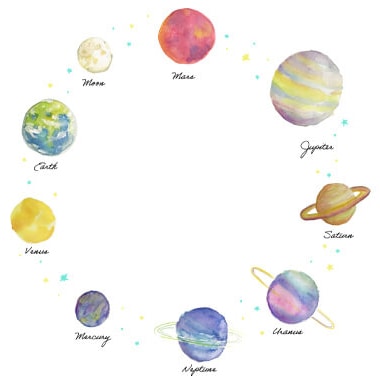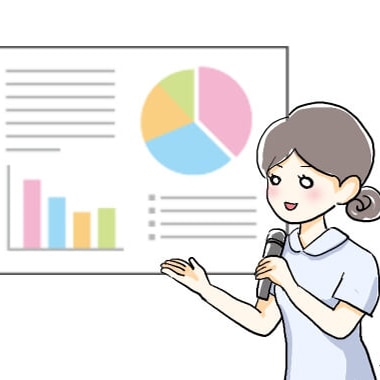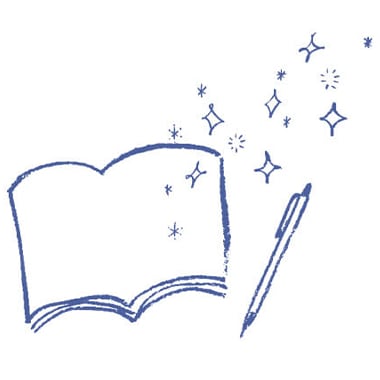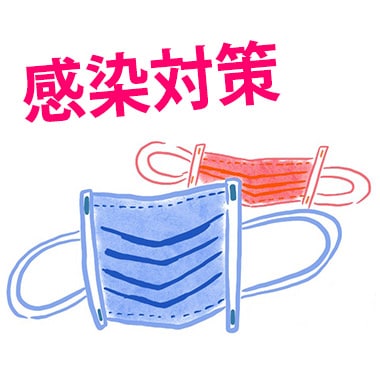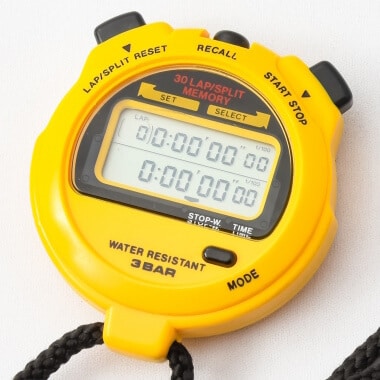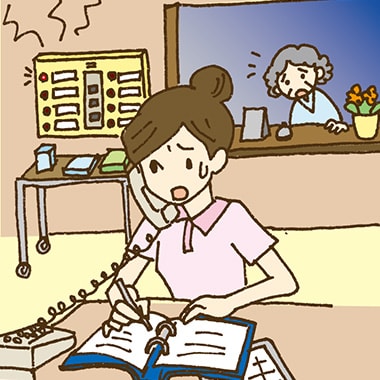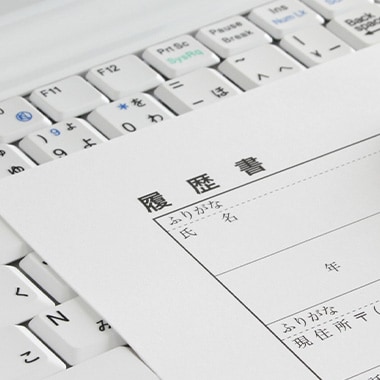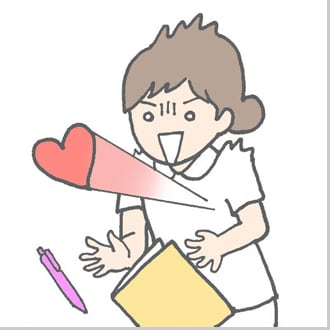1.患者と学生の相性にドキドキする
以前、私が勤務していた病棟では、事前に教員と学生の特性などを情報共有していました。その情報も参考にしながら受け持ち患者を決定する場合が多いのですが、患者と学生の相性は、実習が始まってみないと分かりません。コミュニケーションがとれるかどうかで実習の進み具合は左右されるものです。学生の関わる様子や患者の体調、たとえば「気疲れしていないか」は常に気を配っています。
2.教員とすれ違いで会えない
学校によって実習中の教員配置はさまざまです。常駐している、病棟を掛け持ちしている、講義を担当しているなどで同行できないこともあります。そのため、学生の行動を教員任せにするのではなく、指導者が記録の進み具合も確認しながらアドバイスするわけです。しかし、時間内に教員と会えない時があるため、姿が見えたら「今がチャンス!」とばかりに声をかけ、情報交換をするようにします。
3.記録に追われる学生と、その添削に追われる指導者
日報に加えて、提出される記録は日を追うごとに増えていきます。看護援助やカンファレンスの合間に、指導者は記録に目を通さなければいけません。「気づいたらお昼!」「え?もう学生帰っちゃう!」という時もありますが「何に着目して、どんな援助を考えたのか?」学生の考えを知ることが楽しみなことも。記録を見る時間を確保することは大変です。しかし学生の立場からすれば、記録に書かれた指導者からのコメントが励みになります。
4.計画発表と朝のスケジュール調整が肝!

朝のスケジュール調整がその日を左右するといっても過言ではありません。患者のペースに合わせることも大切ですが、時間内に計画した援助を終えられることも大切だと考えます。
学生が立案した計画がスムーズに進むと、ガッツポーズしたくなるものです。
5.伝える難しさ
臨床で培ってきた経験を、学生に言語化して伝える難しさを感じることがあります。学生は、実習中に「教科書通りにいかないこと」をたくさん経験します。それに対して、指導者だからこそ伝えられる内容があるわけです。伝える難しさを感じながらも、「後になって役に立った」こともあるため、状況判断しながら自分の経験を学生に伝えるようにしています。
具体的に伝えている内容は、周りの動きをみる大切さです。他学生の受持ち患者の援助に一緒に入れるよう調整することで「他の学生がどんなふうに動いているのか?」「どんな関わりをしているのか?」を学ぶ機会になります。臨床に出たら複数の患者を受持つことになるので、周りの動きを気にすることを伝え、かつ時間内に援助が終えられるよう言葉がけをしています。
6.「出来ない」が「出来た」になる喜びを分かち合う
実習指導の醍醐味は、学生の関わりによって患者の「出来ない」が「出来た」に変化する瞬間や、患者が学生へ感謝を伝える場面に立ち会えることです。その場面に立ち会うと、胸が熱くなります。また自分の看護観を振り返る機会にもなります。
7.「実習指導者と学生」の関係から、「同僚」になることへの嬉しさ
「〇〇さんに指導してもらえて良かった」
「ここなら自分のやりたい看護が出来るかもしれない」
と言ってもらえると、やりがいを感じます。
入職時や病棟配属の時に「実習でお世話になりました」と言われて「同僚」になることは、実習指導者だからこそ味わえる嬉しい経験です。
8.自分の指導が「今」に活かされなくても今後につながることを期待している
学生は日々学んでいます。その学びがすぐに活かされることもあれば、後の実習や臨床に出てから気づくこともあります。私のアドバイスに納得していない表情を見ることもありますが、将来どこかの場面で「あの時、指導者にいわれたことだ!」と思い出してもらえたらと願うばかりです。
まとめ

実習指導を通して、自分の看護を振り返ることや学生の成長をともに喜ぶことが出来ます。また、自身の指導方法を見直す良い機会にもなります。そう考えると、実習指導で育ててもらっているのは実習指導者の方かもしれませんね。
ライタープロフィール
【片山はるか】ナースLab認定ライター
三重県鈴鹿市在住。看護師の自立と多様な働き方をサポートしたいという思いがあり、看護師をしながら、看護師ライターやSNS運用、ナースまつり実行委員に携わる。
小児科急性期、糖尿病/呼吸器内科、脳神経内科、現在は手術室に勤務。看護大学で小児看護学助手として研究補助・実習指導の経験もあり。
3児の母。
ブログ:現役看護師/看護師ライター/看護師の起業コンサル@片山はるか
ナースLabホームページ