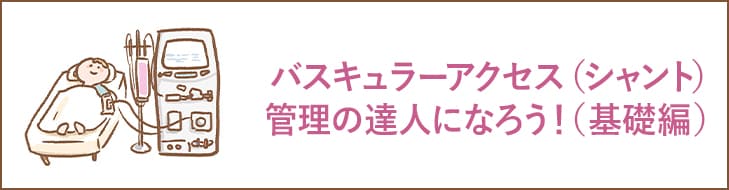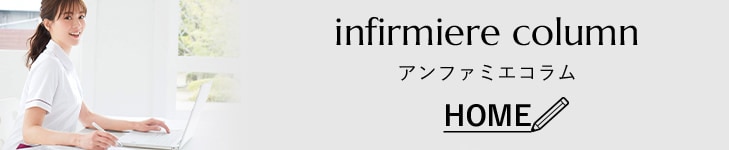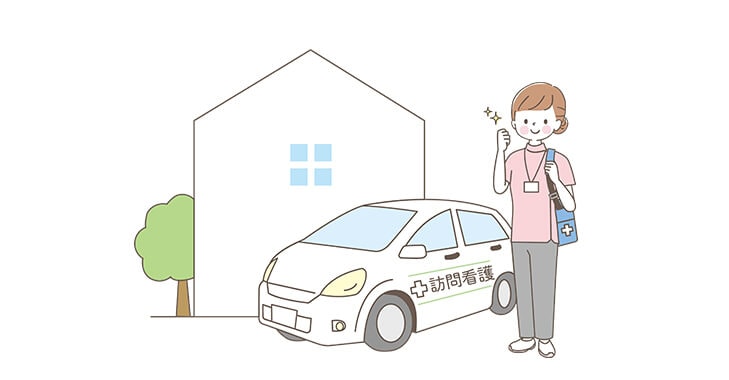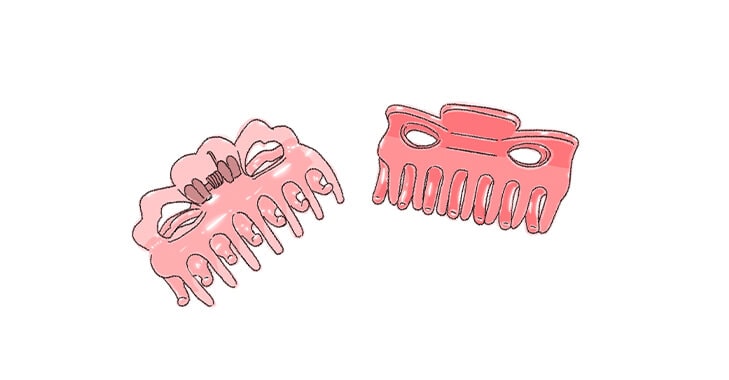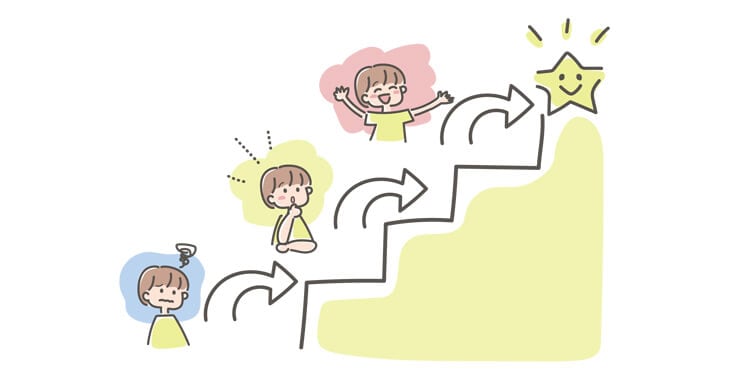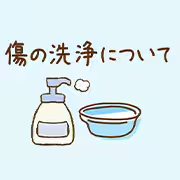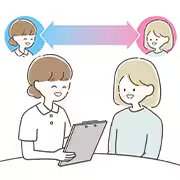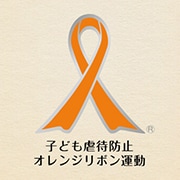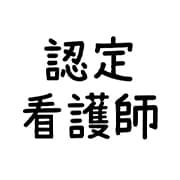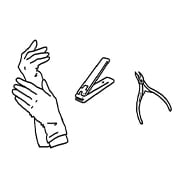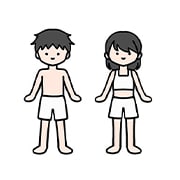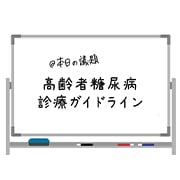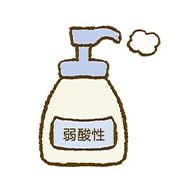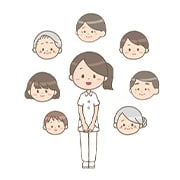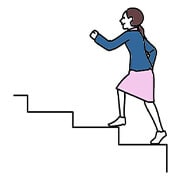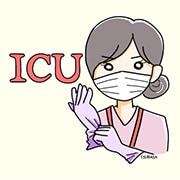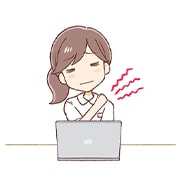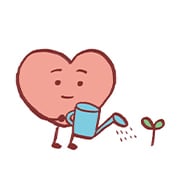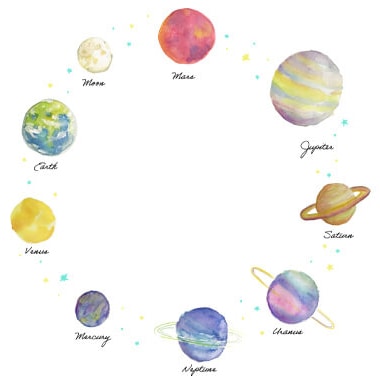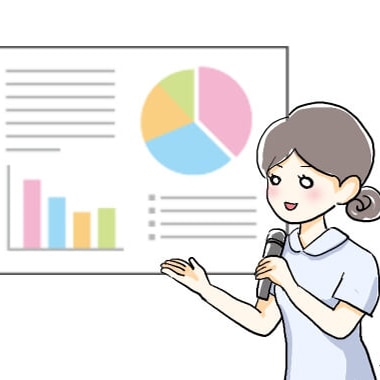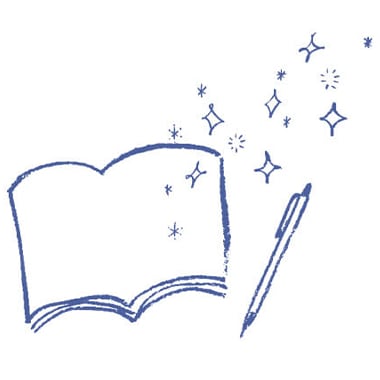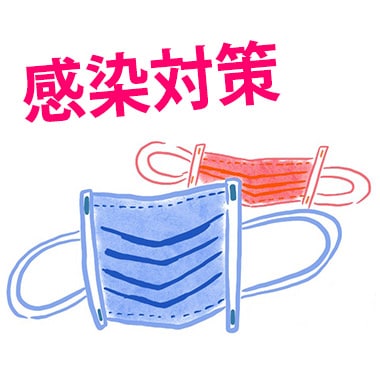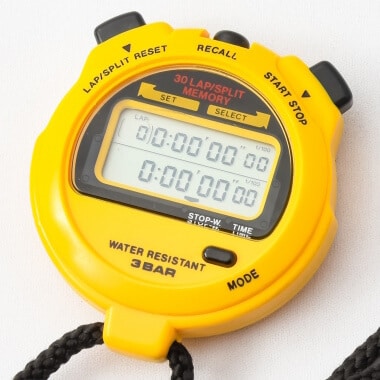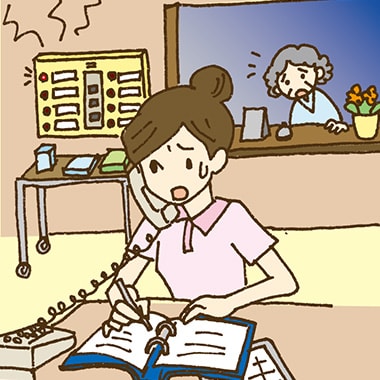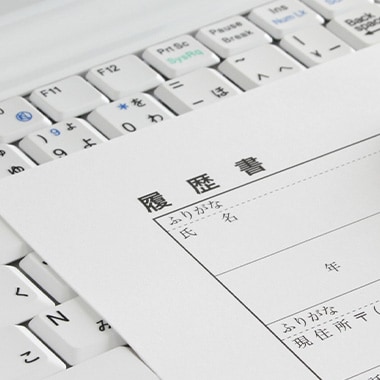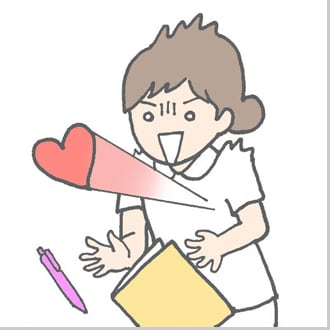1. 閉塞予防と対処法
まずは、閉塞に関する管理法です。
シャント閉塞とは、血管が細くなったり、血栓ができて血液が流れなくなった状態を言います。閉塞したシャントは透析治療では使えないため、患者さんには日常生活での留意点を指導する必要があります。
まず、閉塞予防のポイントはシャントの血流を止める・悪くするような行動を避けることです。具体的には、腕時計や袖口の狭い洋服などでシャントを締め付けない、また重い荷物をシャント肢に掛けない等があります。また、シャント肢で血圧を測定することでシャントの流れを止めてしまうので、このような行動を避けるよう指導しましょう。
シャント閉塞時の症状としては、シャント音が聞こえない、血流を感じない、シャント血管が硬い・痛む等があります。その場合は、速やかに医師やスタッフに伝えるよう指導します。早期に発見できれば早期に対処ができ、侵襲を最小限に抑えることが可能です。
患者さんには普段から自身のシャントを「見て、聞いて、触って」を習慣にしてもらい、何か変化があればスタッフへ伝えるよう指導していくことが重要になってきます。
2.感染予防と対処法
次は、感染に関する管理法です。
現在、透析患者さんの死因第2位は感染症です。1)透析患者さんは、一般的に感染に対する抵抗力が低下しており、感染症に罹患しやすい状況にあります。そのため、シャント感染には十分留意する必要があります。
シャント感染の原因菌は、皮膚の常在菌が最も多く2)それが、穿刺の針穴や皮膚の掻爬等によって菌が体内に入り感染症を起こします。
シャント感染予防には、普段からの保清とスキンケアが重要です。近年はコロナ禍を経験したこともあり、手洗い等基本的な感染予防行動が習慣化されてきました。しかし、先ほど述べたように、シャント感染の原因菌である常在菌を洗い流すためには、透析前の穿刺部位周辺の手洗いも必要になってきます。
また、皮膚の乾燥は皮膚のバリア機能が壊れ、かゆみを伴うため保湿剤を塗布するなどスキンケア法の指導も重要です。最近では、透析治療時に使用するテープの固定力を下げず、皮膚の保湿やテープの剥離刺激から皮膚を守るジェル等の商品も多数発売されています。必要であればそれら利用するのもひとつです。
感染時の症状は、シャント局所では発赤・腫脹・熱感・疼痛、全身症状では発熱・悪寒等です。透析患者は重症化しやすいため、普段から感染時の症状を伝え、疑われた際は速やかに医師やスタッフに伝えるよう指導しましょう。
1)わが国の慢性透析療法の現況(2021年末現在)、慢性透析患者死亡原因
2)透析関連感染の現状とその評価:多施設共同サーベイランスの成果:環境感染誌 Vol.31 no.5、2016
3.出血予防と対処法
最後は、出血に関する管理法です。
前回述べたように、シャントとは本来動脈に流れる血液の一部を皮膚のすぐ下にある静脈に流し、静脈の血流を増加させています。そのため、出血してしまうと必然的にその量は多くなります。また、透析治療では抗凝固剤を使用するため、透析中や透析後しばらくは出血しやすい状態になります。
そこで、まずはおさらいです。
出血には、血液が血管から漏れて組織や体腔内にとどまる「内出血」と、体外に血液が漏れ出す「外出血」があります。シャントの内出血・外出血ともに予防法は、シャントを傷つけない・ぶつけないことです。刃物や鋭利なものを近づけない、シャント肢をぶらぶら振りながら行動しない等、日頃から気をつけるよう指導しましょう。
出血時の対処法としては、出血を止める「圧迫止血」です。自宅など透析施設外で出血した際は焦ってしまうと思いますが、速やかに圧迫止血をするよう普段から指導しておきましょう。
圧迫止血法ですが、まずは内出血・外出血ともに出血部を広範囲に圧迫します。
内出血の場合、どこから漏れ出しているか分からないため、腫脹部を中心に手掌全体で圧迫します。
また、穿刺部の針穴からの外出血の場合も、出血部を中心に3本指で圧迫することが有効です。穿刺をした場合、皮膚の針穴と血管の針穴は10mm前後ずれています。そのため、目に見える出血部や皮膚の針穴だけを押さえるのでは、外出血は止められても内出血をさせてしまうのです。
また、透析治療では針を中枢向きだけでなく、末梢向きに刺すケースもあるため、出血部を中心に3本指で圧迫します。
圧迫の強さですが、内出血・外出血を止めつつ、圧迫している指先等でシャントの流れを感じる強さで圧迫します。
私が患者に指導する際は、患者自身に穿刺部の止血をしてもらいながら、一旦、指先でシャントの流れを感じないくらい強く圧迫してもらいます。そこでゆっくり力を弱めていき、シャントの流れを感じ始めた時点で、内出血・外出血が止められているか確認しましょう。止血できていれば、その強さを覚えてもらうなど、実際に体感してもらっています。
また、出血が止まらない、シャントの流れを感じない際は、速やかに医師やスタッフに伝えるよう指導しましょう。
止血のポイント!
・広範囲に
・出血は止めても、シャントの流れは止めない
まとめ
シャントの管理は看護師だけでなく、患者さんの協力が必要不可欠です。そのためにも、私たち看護師が確かな知識、技術を持ち、患者さんにわかりやすく指導することが重要です。看護師だけでなく患者さんも「シャント管理の達人」になることで、合併症予防に繋がり、シャントを長く保つことができます。本記事が透析看護に日々尽力している方々のお役に立てれば幸いです。
ライタープロフィール
【喜瀬はるみ】
看護師経験34年。透析看護認定看護師。透析患者がその人らしく人生を全うできること、またそれを支える看護師を育成すべく、透析看護に関するセミナー講師活動中。