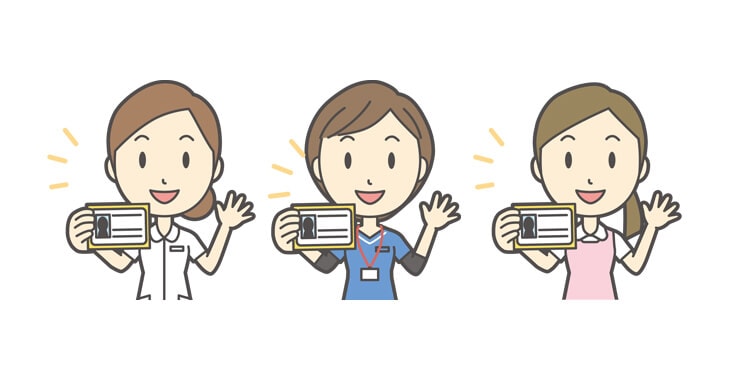1.上司の機嫌と呼吸不全のアセスメントは一緒!? 最終地点から逆算しよう!
師長や先輩が怒る前に、言動や雰囲気を察して、スタッフ間で声をかけ、差し入れを持って行ったり先回りして機嫌を取ったりしていませんか? このような日本代表もビックリするような連携プレーを毎日行っている病棟もあるかもしれません。

これは怒る(最終地点)状態をスタッフ間で共有しており、なおかつ避けたいと思っているからです。つまり最終地点に行かないように逆算して、情報収集し、アセスメントをしています。このような連携プレーは呼吸不全のアセスメントにおいても非常に重要です。
上司が怒るという最終地点は自然と共有できていたりしますが、呼吸不全の定義を曖昧にしていることが多く、最終地点(呼吸状態の悪化による急変)を看護師間で共有できていないように感じます。呼吸不全の状態を共有し、それがどれだけ怖く、避けるべきことだとスタッフ間で認識することで、呼吸不全になる前に自然と情報収集(呼吸音、呼吸回数、呼吸パターンなど)し、重症化が避けられると思います。
それでは、呼吸不全を正しく理解できているか確認していきましょう。
2.呼吸不全は2つだけ!
呼吸不全は大きく分けると1型呼吸不全と2型呼吸不全の2つです。学生時代に「聞いたことある!」と思った方は多いと思います。一方で臨床現場ではあまり、会話にでてこないような気がします。この1・2型呼吸不全は①「低酸素」、②「低酸素+高二酸化炭素血症」の状態です。
・1型呼吸不全は「低酸素(PaO2 60mmHg以下) 」
・2型呼吸不全は「低酸素+高二酸化炭素血症(PaCO2 45mmHg以上) 」
上記が1型呼吸不全と2型呼吸不全の定義です。定義の中の言葉に注目してみましょう。

3.PaO2とSpO2の違い
PaO2は酸素化の指標で、通常値は100mmHg程度です。PaO2(動脈血酸素分圧)と後述するPaCO2(動脈血二酸化炭素分圧)は動脈血液を採血し測定します。動脈血を毎回測定することは、患者にも医療者にとっても負担が大きいです。そのため酸素化の評価にはSpO2がよく用いられています。上記に示したPaO2 60mmHgをSpO2に置き換えると約90%程度です(酸素解離曲線)。

4.PaCO2 換気の指標
PaCO2は動脈血中の二酸化炭素の量を示しています。換気量が増えると、息から体外へ吐かれる二酸化炭素の量が上昇するため、体の中(血中)のPaCO2は低下します。逆に換気量が低下すると、息から体外へ吐かれる二酸化炭素の量が低下するため、体の中(血中)のPaCO2は上昇します。PaCO2は換気の量で変動するため換気の指標です。

5.呼吸不全は進化する!
つまり呼吸不全とは①「低酸素」、②「高二酸化炭素血症」を評価することでわかります。また1型、2型と別れていると一見別のものに見えるかもしれません。しかし、2型呼吸不全は1型呼吸不全が重症化しているので、別のものと捉えるよりも「レベルアップ」、「進化」しているとイメージする方が分かりやすいと思います。

まとめ
今回は呼吸不全とは何かについて解説してきました。あいまいにせずに呼吸不全をしっかり理解し、逆算して呼吸不全になる前に変化に気づきましょう。ただ変化に気づくためには、なぜ低酸素、高二酸化炭素血症になるか原因をきちんと把握する必要があります。次回は低酸素・高二酸化炭素炭素血症の原因について解説していきます。
ライタープロフィール
【オンライン看護学院 ハル】
看護師、保健師、博士(医学)、Instagramer、YouTuber、TikToker
看護大学を卒業後に高度救命センターに勤務。その後、他施設の術後集中治療室及び小児集中治療室に勤務。在職中に医学博士課程を修了。その後、看護大学にて、教育・研究に従事しつつ集中治療室で勤務を兼任。
論文・書籍の執筆多数。
https://note.com/youtube_nursing/n/nc0971df13689