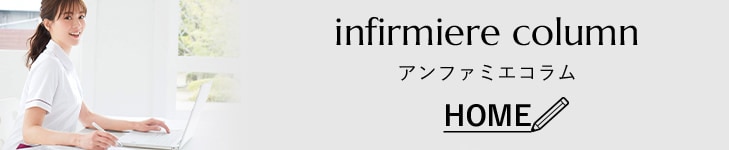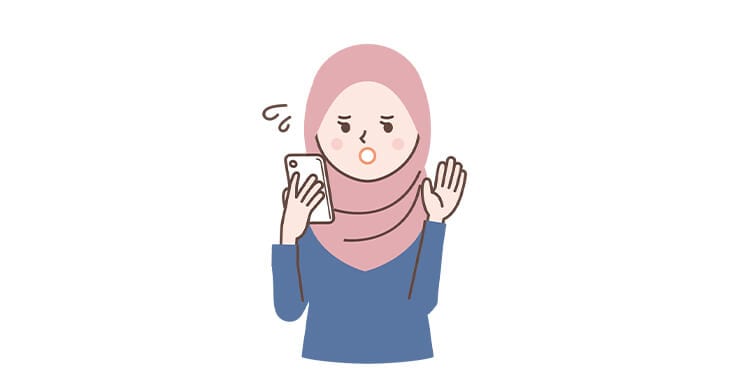1.着用中も着用後も大変なPPE

PPEを着れば汗だく、脱げば化粧はとれ髪は汗でべったり。N95マスクの圧迫で髪や顔にはゴムによる圧迫の跡。鏡を見たら、見たことのない自分の姿にびっくりです。
2.ゾーニングによって物品を取りに行くことができない
一度入ったレッドゾーンから出るには、たとえ患者さんに会わなくてもPPEを脱ぐのがルール。
さあケアをしようと思った時に物品が足りずに泣く泣く着替えることが多々ありました。
3.PPEごしのコミュニケーションの難しさ
高齢の患者さんの場合、PPEを着たままでコミュニケーションズをとるのはなかなか大変。特に声は大声をだしても聞き取ってもらえず、ラップの芯を使って耳元で話すなどの工夫をするスタッフもいました。
4.アプリでクリアできた外国籍の方々との関わり
人種問わず罹患するコロナウイルス。言葉の通じない外国籍の方も入院されます。
言語が通じ辛くても、文明の力「スマホの翻訳アプリ」のおかげでコミニュケーションを容易にとることができました。
5.小児入院は家族も大変
小児の入院に付き添った保護者が感染。元気になり帰宅可能な子どものそばで保護者はぐったりです。同室で入院延長ということは多々ありました。
6.物資不足で選択肢がない
物資不足で、医療物品にも選ぶ余地がありませんでした。工業用のマスクが届いて驚いたことも。でも、ありがたく使わせていただきました。
7.処置から電球の付け替えまで。マルチプレイヤーになる
PPEを着用し患者さんの病室に入れるのは看護師と医師のみ。
通常業務のほか、入院時の保険証確認、ベッドメイク、清掃から部屋の電球の取り替えまでPPEを着た状態で マルチプレイヤーとして立ち回りました。
8.日々の感染者数とコロナ患者数は比例しない

連日報道されたコロナ感染者数。毎日チェックし患者を受け入れられる準備をしていましたが、患者が急増するのは感染者数のピークが過ぎた後。既往疾患もバラバラ。メディア情報があっても対応にはあまり活かせられませんでした。
9.入院したら即確認。退院支援は時間勝負
10日間の隔離期間が終わっても、高齢者など退院調整がうまくいかず帰宅困難となる方もいました。入院当日からしつこいぐらいに隔離期間終了後の方向性を確認して調整していました。
10.支給された手当で業務の危険度を実感

私の勤めていた病院ではコロナ患者対応をすると手当がありました。そのため、通常の月給以外の手当が加算、支給された給料表の合計額を見てびっくり。その分危険な仕事をしていることを改めて感じました。
11.薬剤の金額にびっくりする
使用する抗ウイルス薬の点滴の値段は1本数万円。新薬なのである程度の金額は想定していましたが、実際の金額を聞いてびっくりです。絶対破損させないよう手をふるわせながら点滴準備していました。
まとめ
今回は、コロナ病棟についてご紹介しました。私自身配属前は緊張と不安があり通常とは違う環境になれませんでした。しかし、先行する情報に踊らされず現状の情報を精査し、できることをしっかりやることの大切さを学びました。
情報や基準も時として変化します。変化に柔軟に今あるケアにあわせていく一つの方法として参考になれば幸いです。
ライタープロフィール
【はまなす】ナースLab認定ライター
新潟県出身。2000年卒業し看護師生活をスタート。兄も利用していた小児療育施設に10年勤務を経て現在はクリニックで勤務中。
2022年からライター活動をと看護の二足の草鞋を履きつつ、今はクリニックのマニュアル改定をしながら日々駆けずり回っています。
ナースLabホームページ