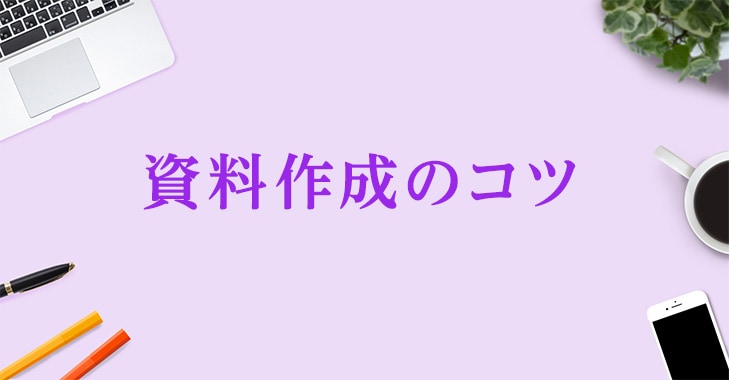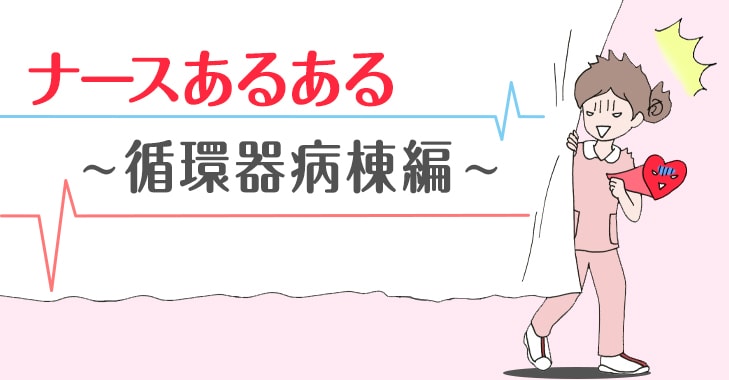1.採血にかける情熱
血液内科では、週に何回も採血が必要な患者さんがいます。数え切れないほど針を刺されてきた血管は、細く、もろくなり、段々と採血が難しくなっていきます。ただし採血データは、その日の治療方針を決めるために必要なもの。たとえ難しくても「後でゆっくりとろう」では間に合わないことも。時には患者さんに怒られながら、それでも採血をしなければなりません。そこが血液内科で働く看護師の、腕の見せどころです。「絶対に成功させる」という採血にかける情熱には、すさまじいものがあります。
2.もはや掃除のプロ?感染源はゆるさない

血液内科病棟では、清潔がとても大切。疾患や治療の副作用により、患者さんはとても感染しやすい状態になります。私たちは病室や病棟の中で、感染源となるものを可能な限り除去しなければなりません。テーブルのわずかなほこりから、シャワー室の排水口にある髪の毛まで、不潔なものを徹底的に掃除していきます。清潔に関する意識の高さは、もはや掃除のプロ。環境整備中に患者さんと会話しながら、いつでも目を光らせています。
3.血液データの低さに慣れていくスタッフ
血液内科では、疾患や治療による骨髄抑制で血球が異常に減少します。白血球数が1,000/μL以下、Hbが5~6g/dL台、血小板数が1万/μLを切る、という数値もめずらしくありません。他の病棟ではおおごとになってしまうようなデータでも、血液内科で働く看護師は動じなくなっていきます。ただしあまりに慣れすぎて、血球減少に鈍感になってしまうという問題も。
4.汎血球減少に目がいきがち
白血球、赤血球、血小板が減ってしまう汎血球減少は、血液内科で避けては通れません。汎血球減少に伴う感染、貧血、出血への関わりは特に大切。指標になる血液データ、関連する症状を観察して、患者さんの状態を把握します。ただし経験が浅いうちは、血球のデータばかりに気をとられてしまうことがあり注意が必要。疾患ごとの症状、薬剤や放射線の副作用など、見るべきデータはさまざまです。もちろん血球減少について関わることが必要ですが、ハッと気づくとそればかりに気を取られていることも。
5.口腔ケアにうるさくなる

血液内科では、化学療法による口腔内の粘膜障害、放射線療法による唾液の分泌低下、白血球低下による易感染など、さまざまな原因で口内炎が起こりやすくなります。口内炎を予防し悪化させないためには、患者さんのセルフケアが大切です。もちろん看護師も観察や介助を行いますが、うがいやブラッシング、舌のケアなど、本人の協力は欠かせません。だるさや吐き気、めまいなどの症状で何もしたくない患者さん。反対に患者さんがいくらつらくても、なんとかケアできるように関わる看護師。うっとうしく思われているかもしれないと感じつつも、今日も患者さんの口腔ケアを応援します。
6.悪寒の出現は血培準備の合図
「寒気がする」と患者さんから訴えがあった場合、血液培養検査の準備を始めるベテランスタッフ。血液内科では、感染が疑われた時の初期対応はとても大切。特に好中球数の低下時は、感染の抵抗力も低いため素早い対応が必要です。患者さんの状態を観察しつつ、血液培養検査や抗菌剤投与など医師の指示を確認していきます。血液内科のデキる看護師のスピードは、周りがついていけないほど。
7.ゆとりがある病棟だと思われがち
「入退院が外科系に比べて少ない」、「手術の出棟がほとんどない」といった理由で、時間に余裕がある病棟と思われることがあります。確かに外科や救命のようなドタバタさはありませんが、それは疾患や治療の特性によるもの。血液内科の看護師には、化学療法や輸血の管理、造血幹細胞移植といった専門性があります。誰に何を言われても、特殊な治療を提供しているという誇りを失うことはありません。
8.患者さん・ご家族に感情移入しすぎる
血液内科では、治療の期間が月単位、年単位と長くなる特徴があります。患者さん、ご家族との関わりが長くなるにつれて、自然と関係が強くなっていきます。患者-看護師関係は保ちつつも、心の中では相手を家族のように見てしまうことも。治療や看護ケアを提供するために、お互いの信頼関係は大切です。もし気持ちを入れすぎてしまう看護師がいたら、優しい目で見守っていきましょう。「それくらい感情移入できるのも、血液内科の魅力だよね」と。
9.マルクの時の寄り添いに看護技術が光る

マルク(骨髄穿刺)は、患者さんの病態を把握するための大切な検査。人によっては定期的に行う必要があります。ただマルクは痛みが強く、麻酔を使おうにも完全には無くなりません。「押されるような感じ」「ゴリゴリされる痛み」と表現はさまざまですが、痛みに耐える患者さんを前に、看護技術が発揮されます。不安を取り除くような声かけをしつつ、手を握ったり、体をさすったり、早く骨髄が採取できるように祈ります。無事に終わり声かけをする時には、まるで激しい戦いを終えた同志のような感覚になることも。
10.意思決定支援に看護の力を発揮
長い療養生活の中で、患者さん、ご家族は大きな意思決定をする場面があります。薬剤の変更や治療の中止など「どうすればいいかわからない」と悩む患者さんやご家族。特に病状が改善しない場合、治療を継続するか中止するかという選択の間で苦しむことも。そんな時に求められる、看護師の意思決定支援という役割。つらい気持ちの共感をベースに「これでいいのかな」と悩みつつ進んでいく、患者さんとご家族を支えます。時には悩んで寝れなくなった患者さんと、夜に何時間も話し合うことも。もちろん血液内科だけに限ったことではありませんが、慢性的な経過をたどる血液疾患の特性上、この場面に出会う看護師は多いはず。チームと連携をとりながら意思決定支援に関わるのは、血液内科の大きな魅力の1つです。
11.まとめ
謎の領域とイメージされやすい、血液内科の看護。今回は共感できるだけでなく、血液内科の知られざる魅力も伝えるエピソードをご紹介しました。もし「血液内科ってよくわからない」と言われたら、この記事をもとに血液内科のことを伝えてあげてくださいね。
~ライタープロフィール~
【野田裕貴】ナースLab認定ライター
大学病院で11年勤務し、血液内科、緩和ケア、ICUを経験。新しい働き方にチャレンジするために、看護師ライターへ転身。現在はWEBサイトへの執筆、看護大学の非常勤教員、老人保健施設の夜勤を兼任するパラレルワーカー。多くの人の最期に関わってきた経験から、人生や命について情報発信するメディアを運営中。
URL:livesmedia.net