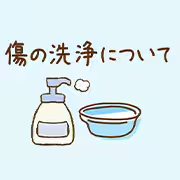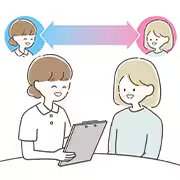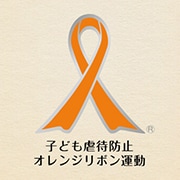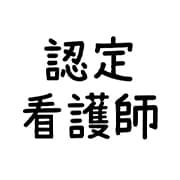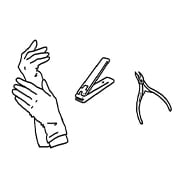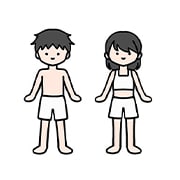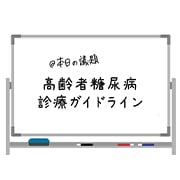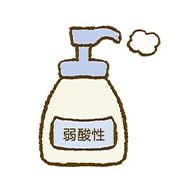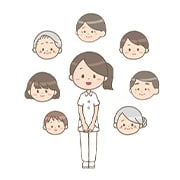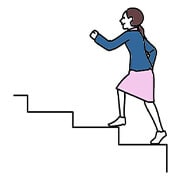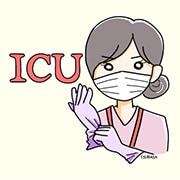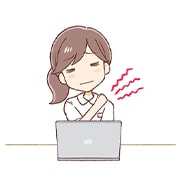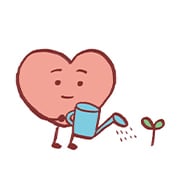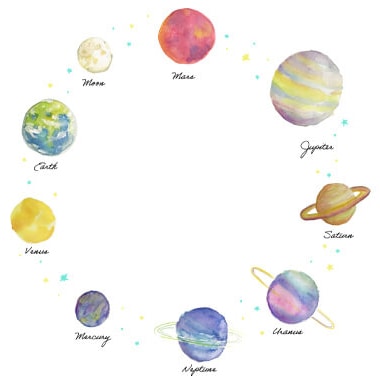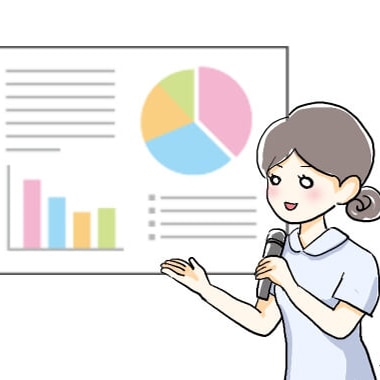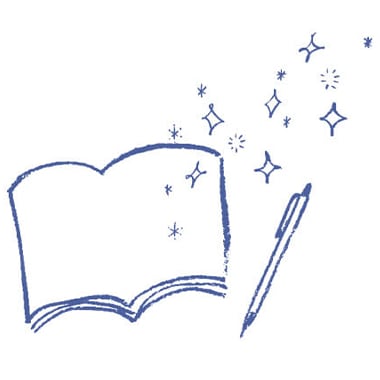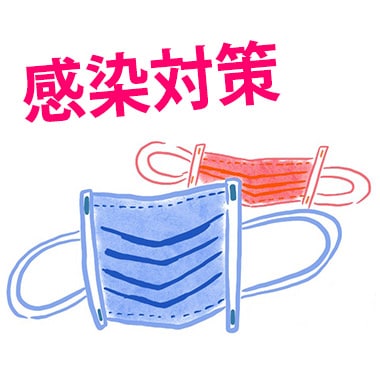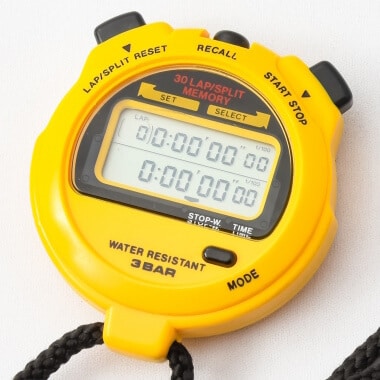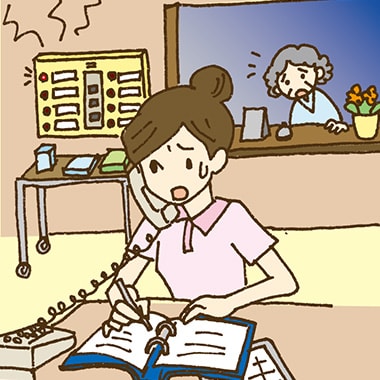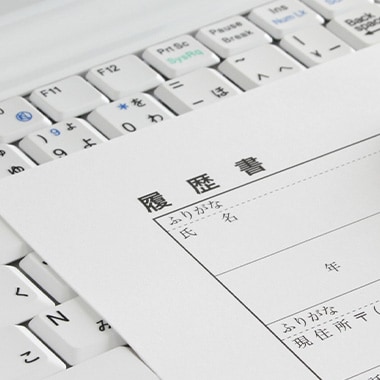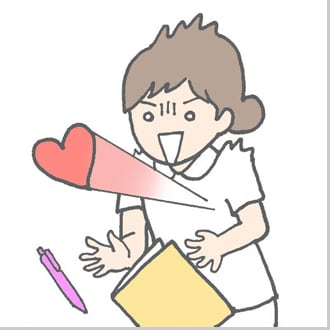【多職種が使っている言語を理解する役割】
多職種と連携していくなかで、まず大切なことは、摂食嚥下に関する共通の言語や知識・技術を持つことです。特に、摂食嚥下分野において看護師が知っておくと良い言語には、喉頭侵入、嚥下反射惹起遅延、知覚閾値の上昇などがあります。
これらの言語は、嚥下内視鏡検査や嚥下造影検査の結果としてもよく使われています。
言語聴覚士の書いている記録で見かけることもあるのではないでしょうか。
喉頭侵入とは、検査食などが喉頭前庭部に侵入することをいいます。食物などが喉頭に流れ込んでいるが、声門を越えての誤嚥は認めない状態のことです。
言い換えれば、「誤嚥はしていないけど、ちょっと危なかったよね」という状態です。
例えば、「喉頭侵入を認めたが、誤嚥なし」と記載されていた場合、「誤嚥がないから、普通に食事を提供して大丈夫」と判断すると誤嚥や窒息の危険性が高くなることがあります。
喉頭侵入があった食形態については、慎重に経口摂取をすすめる必要があるからです。
また、嚥下反射惹起遅延(ゴックンが起こるのが遅い)、知覚閾値の上昇(知覚が悪い)という言語も知っておくとよいでしょう。これらの言語の記載があると、不顕性誤嚥などが生じやすくなるためです。
不顕性誤嚥とは、むせなどの誤嚥の徴候が起こりにくい、または徴候が起こらず誤嚥することを言います。むせない誤嚥と言われたりもします。
不顕性誤嚥では、むせた時にはすでに誤嚥していたり、むせの症状なく誤嚥していたりすることがあるので、咳嗽、痰の量・性状、呼吸数などの呼吸器症状を含めた、日々の誤嚥兆候の観察がより重要になります。
このように、摂食嚥下に関する言語聴覚士が使用している言語を理解することで、看護師としてケアを行う際の判断ができ、言語聴覚士との連携もよりスムーズになります。
言語聴覚士の記録で、わからない言語がないか確認しておきましょう。

【情報を繋げる役割】
次に看護師として大切なことは、日々の看護師が持っている情報を繋げることです。
そのためには、相手が知りたいと思っていることを伝えることと、ちょっとしたことが伝えられる関係性が大切になります。
・相手が知りたいことを伝える
情報を繋げるには、相手の行っていることを理解し、どのような情報が必要か知ることが大切です。言語聴覚士は、嚥下機能評価、嚥下訓練などを日々行っています。
嚥下機能評価では、嚥下内視鏡検査、嚥下造影検査などの客観的な検査を医師とともに行なっています。これらの検査は、多くの場合、言語聴覚士が検査前のベットサイド評価から、どの程度の検査を行うか計画しています。
そして、実際に患者さんに飲んだり、食べたりしてもらいながら誤嚥の有無や、嚥下機能などを画像で評価していきます。
そのため、言語聴覚士は、どの検査が患者さんにとって優先度が高いか判断する情報が欲しいのです。そこで、看護師が持っている情報が役に立ちます。
例えば、患者さんは入院以前からパンが好きで、退院してからもパンだけは食べたいと思っていること看護師が知っていたとします。言語聴覚士へそのことを検査前に伝えておくと、検査時に可能であればパンを使用した評価を計画することができます。
また、言語聴覚士は、夜間の患者さんの状況を知りたいと思っています。特に食形態を変更したときなどは、患者さんの痰の増加や、吸引回数など誤嚥兆候がなかったか気になっていることがあります。看護師が夜間の患者さんの状態を記録に残すことは、言語聴覚士との連携に役立ち、看護師の役割としても大切です。
・ちょっとしたことが伝えられる関係性
普段から、情報を伝えられる関係性も大切です。
看護師は、「なんとなく食べられそう」、「なんとなく食べられなさそう」といった、アセスメントは言語化はできていないけれど、判断していることがあります。
また、言語聴覚士も看護師に「ちょっと伝えておきたい」「ちょっとみておいてほしい」と思うことがあります。
このようなことは記録を残すことができていないこともあるのではないでしょうか。
しかし、普段から、ちょっとした会話ができる関係性があると、「なんとなく」「ちょっとしたこと」を伝えることが容易になります。看護師からも「どんなところをみておいたらいいですか」など、言語聴覚士へ積極的にコミュニケーションを取るようにし、ちょっとしたことが伝えられる関係性を築くようにしましょう。
まとめ
今回は、看護師として多職種のなかでも、特に言語聴覚士との連携で大切な視点をお伝えしました。
摂食嚥下分野では、言語聴覚士以外にも、医師、歯科医師、歯科衛生士、管理栄養士、理学療法士、作業療法士などさまざまな職種との連携が必要になります。
看護師が、問診や普段の患者さんへのケアを通して、得ている誤嚥徴候や食生活に関わる情報を多職種に繋げていきましょう
ライタープロフィール
【西依見子】
食べることと生きる力をつなげるTaste&See 代表。慢性疾患看護専門看護師、摂食・嚥下障害看護認定看護師の資格を用い各施設へコンサルテーションを行っている。「食べたほうがいいのか、食べないほうがいいのか?」といった現場の疑問を解消すべく、スタッフが、口腔ケアを含めた「食べること」への理解を深めるサポートを提供。現在、『コンサルタントナースのスペシャリスト応援ブログ』というブログを配信中。
コンサルタントナースのスペシャリスト応援ブログ